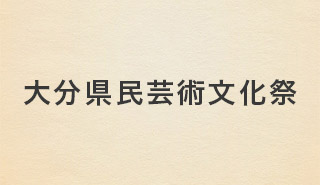- 代表者
- 中村 弘人
- 事務局長
- 髙橋 美和
- 電話番号
- 080-1770-4187
- 設立
- 昭和23年4月1日
- 会員数
- 970名
【令和6年度の活動】
◆課題曲講習会
令和6年5月31日(土)~6月1日(日)に芸術緑丘高等学校音楽ホール、同体育館ほかにおいて課題曲講習会が行われました。講師は本山秀毅先生(合唱指揮者)をお招きして、小・中学校のNHK全国学校音楽コンクール課題曲と高校・一般における全日本合唱コンクール課題曲の指導をしていただきました。多くの小中高生と一般の方々が参加され、本山先生の情熱あふれる指導が行われました。これからコンクールまでの確かな教えを受けることができました。
◆第56回大分県合唱祭
令和6年6月9日(日)に臼杵市民会館大ホールで開催されました。参加団体は25団体、それぞれの団体のカラーが活かされる選曲と音楽表現で、合唱の幅広さを楽しむ一日となりました。ご来場くださったお客様に混じって出演者自身も他団体の演奏を聴き合い、今後の活動への意欲へとつながっています。(以下出演順)豊後大野にじいろ合唱団、ザ・ビーチコール、大分市立南大分中学校合唱部、佐伯市民合唱団コールねむ、エリカフラウエンコール、うすき市民合唱団、大分大学教育学部附属中学校合唱部、男声合唱団豊声会、混声合唱団はじめ、大分市立判田中学校合唱部、コーラス「サラダ・ママ」、大分大学混声合唱団、大分中央合唱団、竹田混声合唱団、大分混声合唱団クールエスポワール、大分市民合唱団ウイステリアコール、女声合唱団ゾネ、別府市立青山中学校合唱部、女声コーラス「朝日」、アンサンブル☆ポラリス、混声合唱団「響」、女声合唱団ラシーヌ、混声合唱団 歌輪、男声合唱団 南蛮コール、混声合唱団 翼 ご出演ありがとうございました。
◆第47回全日本おかあさんコーラス九州支部大会
令和6年6月15日(土)~16日(日)に沖縄コンベンションセンターにて行われました。2日間にわたって行われたこの大会では合計47団体が出場しましたが、大分県合唱連盟からは、女声合唱団 日田コール・アイリスと女声合唱団ラシーヌの2団体が出場し、両団体ともにハイビスカス賞を受賞しました。日田コール・アイリスは8月24日~25日に札幌コンサートホールKitaraで行われた全国大会への推薦を受け、おかあさんコーラス賞を受賞されました。
◆第79回九州合唱コンクール大分県大会
令和6年7月21日(日)にiichiko総合文化センターiichikoグランシアタで行われました。審査員に大庭尋子先生(合唱指揮者)、行天祥晃先生(大分県立芸術文化短期大学教授、東京二期会及び大分二期会各会員)、吉田峰明先生(活水女子大学教授 作曲家)の3名をお迎えして小学生部門1団体、中学校部門11団体、高等学校部門6団体、大学職場一般2団体の審査を行いました。続く九州大会は9月13日~15日に川商ホール(鹿児島市)において、中学校・高校・大職一般部門、また9月28日に宮崎市民文化ホール(宮崎市)において小学生部門が行われました。九州大会では、高等学校部門で1団体が金賞を受賞しました。
◆第26回ヴォーカルアンサンブルフェスティバル
令和7年1月13日(月祝)にコンパルホール文化ホールにて開催されました。講評者には栗栖由美子先生(声楽家 大分大学教授)、辛島慎一先生(大分県立芸術緑丘高等学校指導教諭)の両名をお迎えして、30団体参加による楽しいアンサンブルが披露されました。フェスティバル大賞はmoon light(附属中)が受賞しました。フェスティバル賞は10団体で、大分舞鶴高校音楽部、あおいそらとかにちゃーはん(ウイステリア)、sonnet(上野丘高)、混声合唱団はじめ、藤の花合唱団(ウイステリア)、Collina voce、アンサンブルC.C、Bella voce cantata(東明高)、We♡NANCHU(南大分中)〈以上出演順〉。特別賞の栗栖由美子先生賞は坂中合唱団バーベナ(坂ノ市中)、辛島慎一先生賞はReiwa Jump(臼杵市西中)が受賞しました。なお、3月20日~23日福島県で開催される「第18回声楽アンサンブルコンテスト全国大会」には合唱連盟推薦で、moon light、Bella voce cantata、アンサンブルC.Cが出場されました。
◆2024年度大分県合唱講習会
令和7年1月19日(日)に大分市荷揚複合公共施設多目的大会議室で行いました。講師には作曲家の三宅悠太先生をお迎えして、3年連続初年度の講座でした。小学生から一般まで138名が参加し、「みえないことづけ」より〈1.あいたくて〉〈2.さがして〉を課題曲にして熱のこもった指導が行われました。大画面のプロジェクターに映し出される楽譜に、講師自身が作曲の意図やその表現方法について書き込みながら行われる解説は、視覚的にもわかりやすく伝わり、積極的に歌唱し参加する受講者の姿が印象的でした。また先生のご指導は、合唱メンバーがどのように表現したいかをも大いに採用するもので、主体的に考え、その上で技術的に具現化していく組み立ての過程を教えてくださいました。講習の時間を経るごとに音楽に色合いが生まれ、充実感を感じながら学ぶことができる講習会でした。